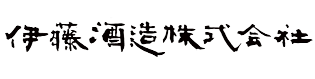episode 2
守を極め、破に挑む
五代目・蔵元杜氏の手が導く“UMAい”
UMAいを追い求める五代目の旅
評価の向こう側に湧いた違和感
そのきっかけは ある一言だった
「飲みやすくて、美味しい。水みたい」
悪気はない むしろ褒め言葉だった
はて?
なぜ 自分はこれほどの時間と想いを込めて
水を造っているのだろう?
その瞬間 五代目の中で眠っていた
何かが ふと目を覚ました
すぐに言葉にはならなかったけれど
どこかにくすぶっていた“探究心”が
静かに動きはじめ 確かに何かが変わり始めた
王道から 自分の”UMAい”へ
五代目として 職人として 王道の酒造り
「正統」と呼ばれる道を 極めようと励んできた
全国新酒鑑評会で金賞を受け 技を磨いた日々
けれどある時 ふと立ち止まる
これは本当に 心を打つ一滴だろうか?
数字や評価のためではなく
“飲んだ人の記憶に残り
心がふっとほころぶような酒”を造りたい
その想いが 新たな旅のはじまりだった
はじまりの問いは やがて原点へ
1847年の決意
初代の挑戦─農の傍らから志へ
五代目の中で膨らみはじめた その問いは
やがて蔵の原点へと導かれていく
1847年 初代・伊藤幸右衛門が
この地で酒造りを始めた それは 農に根ざした
暮らしの中から 志を見出した挑戦だった
自然とともに生きる日々の中で
人の心に届く一滴を求めて
その営みを“酒造り”というかたちで昇華し
新たな価値を生み出そうとしたのだった
二代目〜四代目─受け継がれた問いと技
その後 二代目・三代目は関東への船便出荷
戦時中の廃業と再興という苦難を乗り越え
「地の酒を、地を越えて届ける」挑戦や
「人の想いで蔵を守る」信念を紡いでいく
四代目は吟醸造りを復活させ
全国新酒鑑評会 金賞 受賞蔵へ
名水・智積養水とともに歩む誇りと
技術への探究を深めた
“旨さ”とは何か ─問いが今も生きている
なぜ 酒を造るのか 何をもって旨いとするのか
その問いは 五代にわたって脈々と受け継がれ
いまも蔵の奥に静かに息づいている
暮らしと息づく酒蔵
冬に香る 酒の記憶と 夢のはじまり
五代目・伊藤旬にとって
生まれ育った家そのものが 酒造りの場だった
ひとつ屋根の下に
台所もふたつ 暮らしと仕込みが一体となった家
冬には南部杜氏たちが泊まり込み 酒を醸す
瓶詰めやラベル貼りを手伝いながら
湯気と発酵の匂いに包まれる──
そんな中で育った彼は
科学者になりたい 発明家になりたいと夢見た
その“想像と探究”の心が
蔵元杜氏としての現在につながっている
杜氏ととも歩み 後に蔵元杜氏 職人へ
「企画する職人」としての挑戦
外部杜氏から蔵元が醸す時代へ
その過渡期に五代目は
「全量三重県産米による酒造り」を打ち出す
コンビニ立ち上げなど社外での事業開発経験が
“伝える設計者”としての力に昇華した
慕蔵構想と「語らう蔵」の実現
岩手から来る南部杜氏に師事し
仕込みのひと手ひと手から
技術だけでなく 魂や空気感までも
肌で感じ 染み込ませていく
そして 醸されていく“自分だけの感覚”
「この蔵は単なる生産の場ではなく
文化を醸す場にできるはずだ」 という
想いが芽生えていった
「酒は人と語らうもの。 だからこそ、
蔵そのものが語る空間でありたい。」
五感と物語を共有できる空間を作りたい──
その思いが 現在の「慕蔵」や体験プログラムへと発展していった。
地の力を映す酒 感性の酒
伊藤酒造で造る酒はすべて 三重県産米使用
この土地の“生きものたち”と共に発酵し
究極の地酒を目指す
「この地で、なぜ酒を醸すのか」
その答えが 米や水 風土
そして“飲む人の笑顔”に宿っている
スパークリング、熟成、とびきり燗……
「こんな瞬間にこそ この味を」という
風景から生まれた酒たち
生きざまを注ぐ“ひとしずく”
仕込みの蔵だけでなく、売り場のカウンターに立ち、 誰に、どんな顔で、どんな時間に飲まれるのかを想像する。
評価ではなく、笑い合える“旨いね”のひとしずくを。
そんな“感性に残る旨さ”を届けたい。
それが五代目の探究の原点であり、いまも続く挑戦です。
酒は “生きざま”の結晶
問い、迷い、遊び、語る。
それをすべて醸し出した一滴が、伊藤酒造の“UMAい”。
今日も五代目は、誰かの笑顔を想像しながら
酒蔵と売場を往復している。
響き合うひとときを信じて──。
─
五代目の旨いを生む “自然との対話”という哲学
米と酵母を自らの力で語らせる
やがて その探究は──
「整える」から「導く」へ
“引き出す”ための醸しへと
静かにかたちを変えていく